読んだ本


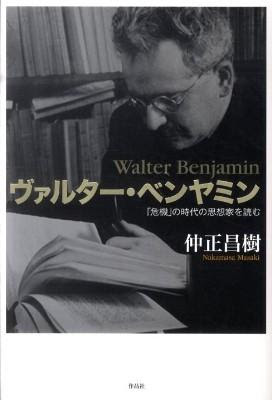
つづきを読み進めた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
昨日の本を読み進めようと思ったところ、鞄に入れ忘れてしまったので別の本を読むことにした。
最近は再びノンフィクションに興味を持つようになってきた。
ノンフィクションは小難しい抽象的な議論がないのですらすら読める。
『書物の破壊の世界史』は、手前味噌ながら、最近本に関する知識が増えてきたと感じているので、過去にどういった本がどのような理由で破壊(=焚書)されたのか好奇心がわいてきた。
今日はまず50ページほど読んだあとにナチスと焚書に関するページを読んだ。
まず驚いたのが、ナボコフがメモリアルホールのなかで学生に向かって『ドン・キホーテ』を燃やすように求めた、という事実についてであった。
なぜ『ドン・キホーテ』なのか。残念ながら『ドン・キホーテ』の前半で挫折してしまった自分には理解できなかった。本書は分厚いので、これはひとつの伏線として、これからじっくり読んでいきたい。
ナチスの標的はユダヤ教の聖典、タルムードや共産主義に関する書物であった。
また、ドイツの過去の失敗について書かれていた書物もその対象であったそうである。
本は「記憶装置」としても機能する。本書ではフロイトの「父親殺し」に倣って「記憶殺し」と表現されていた。
歴史に弱い自分は、本当のところ、なぜ共産主義がこうも忌避の対象となっていたのかがいまいちピンとこなかった。
ドイツが苦しいのはユダヤ系の資本家のせいだ、という風潮があったみたいだが、嫌悪の対象は資本主義ではなかったのか。ヒトラーは明らかに共産主義を嫌っていた。
このあたりは勉強をしないと見えてこないだろう。
・・・
フォースターの評論では文化と自由について考えさせられた。
ある側面では、いまではサブカルチャーと呼ばれる文化への批判や、未来の文化に対する懸念が読み取れた。
いわゆる「3S政策」に対する懸念である。それが今の日本と重なって見えた。
・・・
『ヴォルター・ベンヤミン』では引き続き『翻訳者の課題』の講義を読んだ。
二流はともかく、一流の芸術家は普通、「見られること」を意識して製作を行わない。(本書の文脈に沿って言えば)
ゆえに、文学作品を翻訳する者は、解説書の翻訳と同じように、単なる「情報伝達」としての翻訳では意味を成さないとベンヤミンが考えているということが理解できた。
「情報伝達」としての翻訳は、「見てもらうこと」がそもそもの前提となっているためである。
つまり翻訳者の課題は、文学作品に秘められている「なにか」を見つけ出さなければならないということでもある。
形式には規則性が伴う。普通に考えれば形式なき美しい音楽は存在しない。
翻訳を生業としている人からすればたまったものではないが、文学と崇高について、カントの考察と交えながらいろいろと考えさせられるものであった。
例えば「合目的性」の備わっている文学作品における「目的」とはそもそもなにか。
この点については、さすがに本書のなかでは明言することは避けられていた。
この問いはあまりにも深すぎる。
湿気と暑さにうんざりしたが、今日はそこそこ読書で楽しめた一日であったと感じている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
関連図書
イアン・カーショー『ナチ・ドイツの終焉1944-45』白水社 (2021)