読んだ本

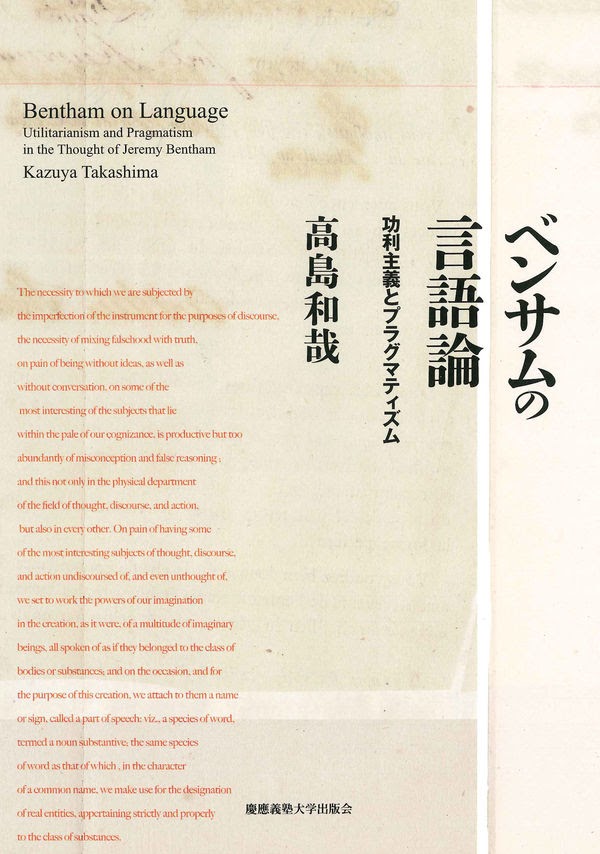
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
失われた30年の原因は、小室直樹の見立てでは「アノミー」だとされているが、自分のなかではいまいちパッとしない理解のままである。
小室直樹『危機の構造』はそれが分析されている内容となっているが、読むのがしんどくなり売ってしまった。
この『橋爪大三郎の政治・経済学講義』はそんな小室直樹の本より幾分か読みやすい。
また、橋爪大三郎氏が小室直樹の教え子ということもあってか、ふと気になったので読んだ。
読んでみると、なかなか複雑で(当たり前ではあるが)、問題はソ連の崩壊であるとか、日本の外交の失敗であるとか、様々な原因があるようだな、と思わせるような内容であった。
宗教への理解のなさもまた原因かもしれない。教育の問題も含めて考えると文章が止まらないので割愛。この本は読みやすく、様々な年齢層に読まれることを期待。
・・・
『ベンサムの言語論』は260ページまでたどりついた。
今日は「法の科学」に関する内容に斬り込んでいった。
"すべての科学はその形而上学を有するのであり、その科学に特有の観念を表す、その科学に特有の用語の集まりをもたない科学など存在しない。・・・・・・立法 [ の科学 ] もまた他のもの [ 科学 ] と同様、その形而上学を有している。そして、他の場合と同様、これ [ 立法の科学 ] を改善するためには、経験と形而上学が手を取り合って進まなければならない。" P230 (『ベンサムの言語論』)
本書の前半ではベンサムの方法論は3つの特色があると書かれていた。
・経験主義的であること
・還元主義的であること
・量的であること
そして、科学的に物事を考えるには言葉の定義を厳密にしなければならないとベンサムは考えていた。
本書を読み進めていくと、法律も言語によって定義されていく以上、ベンサムは容赦なくその厳密性というものを念頭に置きながら考察を続けていった様子が伝わってきた。
ベンサムは「刑法」と「民法」という言葉にも半ば攻撃的に吟味していく。
ベンサムは、法律の本質は「命令的規定」にあると考えた。
法は主に4つのタイプがあり、
1.すべし
2.すべからず
3.を差し控えてもよい
4.してもよい
3と4は1の存在なしには有り得ず、ベンサムは、「観察者は「1.すべし=命令的法」にのみ注目すべきである」と述べた。
次にベンサムはこれを踏まえ、「命令的法は刑法のことではないのか?そうであれば実質的に法システムの大部分は刑法から成り立っている」と考え、刑法と民法の関係性について考えた。
そして、「二分法」を用いて徹底的に法を分類していく。
"しかしながらベンサムの考えでは、そのような疑問は、刑法や民法という名前で呼ばれる個別的法が存在するという前提の上に成り立つ疑問であって、そうした前提自体がそもそも誤りである。というのも、刑法という名の個別的法や民法という名の個別的法が独自に存在するわけではなく、論理的観点からみた場合、むしろ個別的法としての「命令的法」の構成要素として「刑法的部分 penal branch」と「民法的部分 civil branch」という二つの要素が存在するというのが真相であるからだ。" P235 (『ベンサムの言語論』)
換言すれば、ベンサムは、すべての法律には必然的に民法的な性質と刑法的な性質が同時に存在すると考えた。
次にベンサムは、主権者の意志が命令的言語によって示されている刑法的部分こそ、あらゆる個別的法の本質にあたると考え、違反行為を分類することが「法の分類」であると考えた。
そのあとはフランス人権宣言の批判に入っていくが、一旦自分の頭を再度整理してから書こうと思った。
つづく
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
関連図書