読んだ本
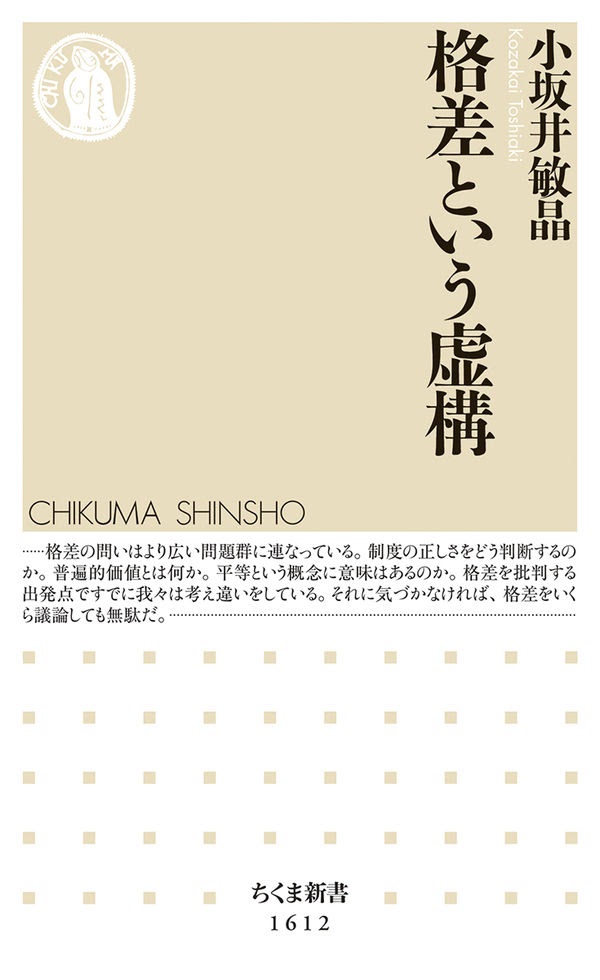

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日記
『格差という虚構』を再読。
概ねマイケル・サンデル氏と同じように、能力というものは統計データから大局的に見れば環境や遺伝に起因するので、格差というものはそもそも決定論的に、不動の「ヒエラルキー」のように存在しているという見方であった。(流動性がないこと)
小坂井氏は「能力の差を正当化するために格差という虚構がつくられる」と書いている。
では何のために能力の差を正当化したいのか?
今日はよく分からなかった。初見の頃は遺伝と環境がいかに格差というものを生み出すのかという意識で読んでいたはずなので、見逃している点は多かったように思う。
個人的な推測としては、社会の安定性を保つために能力の差を正当化するという見方である。
つまり「努力によって夢は叶う」という物語を潰してはいけないから、努力が報われることを否定しないことによって競争の原理を維持しようとしているのではないかという推測である。
または「自己責任」の論理を崩壊させないため、か。
『責任という虚構』は、社会が責任を誰かに背負わせるために、因果律を無視して責任が「正当化」されるということを小坂井氏が指摘した本であった。
能力とはそもそもなにか、という定義は難しいが、経済的な豊かさが能力と無関係であるならば、何によって貧困層を救う論理が成立するのだろうか。考えれば頭が痛くなる。
結局『格差という虚構』は何がしたいのか?これはもう一度最後まで読まなければ分からないが、おそらく社会にはヒエラルキーというものが存在しているよ、というメッセージなのである。しかしこれを公に発信すると「努力をしても報われない=統計的に社会上昇はほとんどない」というメッセージが貧困層への希望を奪うことになる。
とはいえ「カースト制度」並みの威力はないように思われる。
格差ではなくヒエラルキーが存在していると認識し、自分は絶対に上昇してみせると決意を固めれば必ず例外は発生するはずである。
・・・
『目的への抵抗』は、世界が資本主義という営利目的で機能しているなか、コロナ禍によって移動制限をされ、アガンベンのいう「剥き出しの生=ただ生きているだけで価値がある」ことになった時についての講義が進む。
ただ生きているだけで価値があることは否定しないが、「ただひらすら食べる、寝るの繰り返し」が人間の価値であっていいのか?という問題提起であった。
移動の自由というものが人間の根源的な欲求だったのではないか、ということが示唆された。
刑務所は移動の自由が奪われる。これが実はそうとうにきついらしく、衣食住があっても「移動の自由」が無いことによっていかに人間が苦しむのかを、ロックダウンの時を振り返りながら読者に語りかけ、人間の本当の価値というものを考えさせるような構成となっていた。
自分はカントと話を結びつけた。
目的にはつねに計算がつきものである。計画なしに目的の達成はない。
目的は打算的とも言える。そして打算は帰結主義とも重なる。それはカント的にはNOである。
だから目的への抵抗というのは、倫理学の話になる。
個性的な哲学者でも、どこかで彼らは考えが一致することが多い。
ここが面白いところである。
つづく
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
関連図書